リフォームの際、意外と見落としがちな「カーテン」。
我が家の場合、工務店さんの見積書にはカーテンが含まれていなかったため、相談してカーテン専門店をご紹介いただきました。
これまでの賃貸生活では、ホームセンターなどで既製品のカーテンを選んでいましたが、今回はリフォームを機に「初めてのオーダーカーテン」に挑戦。結果的に、仕上がりも機能性も大満足のカーテン選びとなりました。

リフォームの際、意外と見落としがちな「カーテン」。
我が家の場合、工務店さんの見積書にはカーテンが含まれていなかったため、相談してカーテン専門店をご紹介いただきました。
これまでの賃貸生活では、ホームセンターなどで既製品のカーテンを選んでいましたが、今回はリフォームを機に「初めてのオーダーカーテン」に挑戦。結果的に、仕上がりも機能性も大満足のカーテン選びとなりました。
カーテンを取り付けた場所はこの6か所
- リビングの掃き出し窓(南側)
- キッチン横の勝手口(南側)
- リビングの腰窓(東側)
- 洋室3部屋の腰窓(北側×3)
それぞれの方角や用途に合わせて、色や機能を重視して選びました。遮光カーテンは風水的に良いとされる色を参考にし、レースカーテンには「ミラーレースカーテン」を採用。外からの視線を遮りつつ、室内から外は見えるという優れものです。
悩んだのはリビング東側の腰窓
いちばん迷ったのが、リビングの東側にある腰窓。
選択肢は以下の4つでした。
- カーテン
→ 見た目にボリュームが出てしまい、ちょっと圧迫感が…。 - ロールスクリーン
→ 一枚なので開ける・閉めるのどちらかだけ。朝の陽ざしをうまく取り込めず。 - ブラインド
→ ロールスクリーンと同じく断熱性や調整の面で少し不安。 - ローマンシェード
→ お店で初めて知ったスタイル。レース生地とカーテン生地を二重で設置できて、ヒダのボリュームもなくてスッキリしているところが気に入って、即決しました。
ローマンシェードに決定しました。ローマンシェードもお洗濯が可能で、見た目もすっきり。東からの朝の光を柔らかく取り込めて、とても気に入っています。設置の際にひとつ注意したポイントは、「窓枠よりどれくらい長くするか」ということ。
我が家では、子どもの安全面を考えて窓の前に家具は置かないようにしていたため、朝の日差しがしっかり遮れるように、シェードの丈をやや長めにしました。
特に東側の窓は、季節によって朝日がまぶしく差し込むので、丈の調整はとても大切なポイントだったと感じています。
また、カーテン屋さんが採寸と見積もりのために訪問してくださった際に、そうした生活スタイルや採光の悩みをお伝えしたところ、とても丁寧に相談にのっていただき、的確なご提案をしていただけました。プロの目線からアドバイスを受けられたことで、安心して決めることができました。
リビングの掃き出し窓&勝手口
リビングの大きな掃き出し窓は、カーテンを2枚にしてボリュームを調整。
一方、キッチン横の勝手口は開き戸のため、設置場所に梁もあり、カーテン以外の選択肢がありませんでした。ここにもミラーレースと遮光カーテンを設置し、視線と日差しをコントロールしています。
正直、「ここもローマンシェードだったらなあ…」と思いましたが、構造上仕方なしです。
洋室3部屋の腰窓の工夫
- 寝室となる一番奥の洋室は大きめの腰窓 → カーテンを2枚にしてバランスを。
- 他2つの洋室は窓が小さいため → 1枚カーテンにし、壁側のタッセルでまとめる仕様に。
開閉のしやすさと、部屋ごとの役割に合わせたスタイルにしました。
カーテンを選ぶ前にチェックしておくと安心なポイント
- 壁に下地補強があるかどうかの確認(特にカーテンボックスや重たい生地の場合はカーテンを開けてタッセルで束ねると片側に大きな負荷が長時間かかるため要注意、工務店さんに要相談です)
- カーテンレールの取り付け位置(天井付けにすると空間が広く見える効果がありますが、中古マンションのリフォームでは構造上できない場合もあります。その場合は、工務店さんと相談してできる範囲での調整や妥協が必要になることも。我が家は相談もせずに現状の位置に納得しました。)
- ヒダのボリューム感(ヒダ倍率1.5倍とヒダ倍率2倍で印象が全く違います)
カーテン屋さんに来店して良かったこと
カーテン専門店に足を運んで本当に良かったと思いました。
実際にカタログだけでは分からない「手触り」「光の透け方」「重さ」「開閉のしやすさ」などを確認できたのは、大きな収穫でした。
中でも印象的だったのは、同じ生地でもヒダの数によって見え方が全く違うということ。
今回は、「1.5倍ヒダ」と「2倍ヒダ」の両方を見比べてみましたが、印象はかなり異なります。
1.5倍ヒダは、生地の使用量が窓幅の1.5倍で、2つ山のヒダが特徴。すっきりとした印象で、一般的によく使われるスタイルです。
一方の2倍ヒダは、生地を窓幅の2倍使い、3つ山で仕上げるスタイル。ドレープの陰影がより深く出て、ボリューム感や高級感があります。
ただし、生地の量が増えるぶん、カーテン自体の「重さ」や「費用」も比例してアップする点は要注意。取り付け場所やカーテンレールの強度、使い勝手にも関わってきます。
実際に見て、触って、動かしてみて、「なるほど、こんなに違うんだ」と納得できたのも、店舗での体験があったからこそ。
こういう細かな違いは、ネットやカタログではなかなか分からないので、やはり実物を見ることの大切さを実感しました。
費用面では、決してハイグレードなものばかりを選んだわけではありませんが、無理のない予算のなかで、我が家にとってバランスの良い選択ができたと思っています。
おわりに
カーテン選びは、インテリアとしての印象だけでなく、機能性や光の調整、断熱・遮光、さらには防犯にも関わってきます。
リフォームのタイミングだからこそ、生活スタイルや部屋の使い方を見つめ直しながら、最適なカーテンを選べました。
これからリフォームを考えている方や、カーテンの購入を検討している方の参考になれば嬉しいです。
今後もこうした体験をブログで紹介しながら、楽しく情報発信を続けていきたいと思っています!
リフォームの際、意外と見落としがちな「カーテン」。
我が家の場合、工務店さんの見積書にはカーテンが含まれていなかったため、相談してカーテン専門店をご紹介いただきました。
これまでの賃貸生活では、ホームセンターなどで既製品のカーテンを選んでいましたが、今回はリフォームを機に「初めてのオーダーカーテン」に挑戦。結果的に、仕上がりも機能性も大満足のカーテン選びとなりました。
カーテンを取り付けた場所はこの6か所
- リビングの掃き出し窓(南側)
- キッチン横の勝手口(南側)
- リビングの腰窓(東側)
- 洋室3部屋の腰窓(北側×3)
それぞれの方角や用途に合わせて、色や機能を重視して選びました。遮光カーテンは風水的に良いとされる色を参考にし、レースカーテンには「ミラーレースカーテン」を採用。外からの視線を遮りつつ、室内から外は見えるという優れものです。
悩んだのはリビング東側の腰窓
いちばん迷ったのが、リビングの東側にある腰窓。
選択肢は以下の4つでした。
- カーテン
→ 見た目にボリュームが出てしまい、ちょっと圧迫感が…。 - ロールスクリーン
→ 一枚なので開ける・閉めるのどちらかだけ。朝の陽ざしをうまく取り込めず。 - ブラインド
→ ロールスクリーンと同じく断熱性や調整の面で少し不安。 - ローマンシェード
→ お店で初めて知ったスタイル。レース生地とカーテン生地を二重で設置できて、ヒダのボリュームもなくてスッキリしているところが気に入って、即決しました。
ローマンシェードに決定しました。ローマンシェードもお洗濯が可能で、見た目もすっきり。東からの朝の光を柔らかく取り込めて、とても気に入っています。設置の際にひとつ注意したポイントは、「窓枠よりどれくらい長くするか」ということ。
我が家では、子どもの安全面を考えて窓の前に家具は置かないようにしていたため、朝の日差しがしっかり遮れるように、シェードの丈をやや長めにしました。
特に東側の窓は、季節によって朝日がまぶしく差し込むので、丈の調整はとても大切なポイントだったと感じています。
また、カーテン屋さんが採寸と見積もりのために訪問してくださった際に、そうした生活スタイルや採光の悩みをお伝えしたところ、とても丁寧に相談にのっていただき、的確なご提案をしていただけました。プロの目線からアドバイスを受けられたことで、安心して決めることができました。
リビングの掃き出し窓&勝手口
リビングの大きな掃き出し窓は、カーテンを2枚にしてボリュームを調整。
一方、キッチン横の勝手口は開き戸のため、設置場所に梁もあり、カーテン以外の選択肢がありませんでした。ここにもミラーレースと遮光カーテンを設置し、視線と日差しをコントロールしています。
正直、「ここもローマンシェードだったらなあ…」と思いましたが、構造上仕方なしです。
洋室3部屋の腰窓の工夫
- 寝室となる一番奥の洋室は大きめの腰窓 → カーテンを2枚にしてバランスを。
- 他2つの洋室は窓が小さいため → 1枚カーテンにし、壁側のタッセルでまとめる仕様に。
開閉のしやすさと、部屋ごとの役割に合わせたスタイルにしました。
カーテンを選ぶ前にチェックしておくと安心なポイント
- 壁に下地補強があるかどうかの確認(特にカーテンボックスや重たい生地の場合はカーテンを開けてタッセルで束ねると片側に大きな負荷が長時間かかるため要注意、工務店さんに要相談です)
- カーテンレールの取り付け位置(天井付けにすると空間が広く見える効果がありますが、中古マンションのリフォームでは構造上できない場合もあります。その場合は、工務店さんと相談してできる範囲での調整や妥協が必要になることも。我が家は相談もせずに現状の位置に納得しました。)
- ヒダのボリューム感(ヒダ倍率1.5倍とヒダ倍率2倍で印象が全く違います)
カーテン屋さんに来店して良かったこと
カーテン専門店に足を運んで本当に良かったと思いました。
実際にカタログだけでは分からない「手触り」「光の透け方」「重さ」「開閉のしやすさ」などを確認できたのは、大きな収穫でした。
中でも印象的だったのは、同じ生地でもヒダの数によって見え方が全く違うということ。
今回は、「1.5倍ヒダ」と「2倍ヒダ」の両方を見比べてみましたが、印象はかなり異なります。
1.5倍ヒダは、生地の使用量が窓幅の1.5倍で、2つ山のヒダが特徴。すっきりとした印象で、一般的によく使われるスタイルです。
一方の2倍ヒダは、生地を窓幅の2倍使い、3つ山で仕上げるスタイル。ドレープの陰影がより深く出て、ボリューム感や高級感があります。
ただし、生地の量が増えるぶん、カーテン自体の「重さ」や「費用」も比例してアップする点は要注意。取り付け場所やカーテンレールの強度、使い勝手にも関わってきます。
実際に見て、触って、動かしてみて、「なるほど、こんなに違うんだ」と納得できたのも、店舗での体験があったからこそ。
こういう細かな違いは、ネットやカタログではなかなか分からないので、やはり実物を見ることの大切さを実感しました。
費用面では、決してハイグレードなものばかりを選んだわけではありませんが、無理のない予算のなかで、我が家にとってバランスの良い選択ができたと思っています。
おわりに
カーテン選びは、インテリアとしての印象だけでなく、機能性や光の調整、断熱・遮光、さらには防犯にも関わってきます。
リフォームのタイミングだからこそ、生活スタイルや部屋の使い方を見つめ直しながら、最適なカーテンを選べました。
これからリフォームを考えている方や、カーテンの購入を検討している方の参考になれば嬉しいです。
今後もこうした体験をブログで紹介しながら、楽しく情報発信を続けていきたいと思っています!

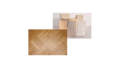
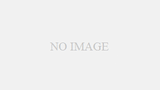
コメント